1.新規な脱水縮合剤の開発
酸アミドはタンパク質を構成するアミノ酸単位の結合として,エステルはリン脂質を構成するグリセリンと脂肪酸やリン酸を繋ぐ結合として,私たちのからだの中で極めて重要な役割を担っています.また,医薬品や化成品に目を向ければ,アスピリンやアセトアミノフェンのような解熱鎮痛剤,βラクタムやマクロライド系といわれる抗生物質群からナイロン,ポリエステルなどの高分子まで,幅広く分布する最も基本的な構成単位の一つであるといえます.
酸アミドやエステル結合を構築するための最も直接的で一般性の高い方法は,カルボン酸の活性化を伴う脱水縮合反応です.過去100年以上にわたって多くの縮合剤が開発されてきましたが,現在,研究や産業面で頻繁に利用されている縮合剤は数種に過ぎません.当研究室では,新規な脱水縮合剤DMT-MMを開発し,この化合物が従来の脱水縮合剤にはない優れた反応性を有することを見出しました.すなわち,もともと脱水縮合反応は水を嫌うので,通常は乾燥条件下で行うべきですが,DMT-MMを用いれば,水やアルコールを溶媒にしても,アミンとカルボン酸とを混ぜるだけで,収率良く酸アミドが得られることを明らかにしました.さらに,1)水やアルコール以外の多様な中性溶媒中で利用可能,2)室温,短時間,中性条件下,高収率,3)吸湿性や刺激性の無い安定な固体,4)副生成物の除去が容易,5)低価格で製造可能,6)添加剤が不要,等の利点を有し,実用面から将来性の期待できる反応剤であることを示しました.実際,この試薬は既に国内外で市販され,その利用が徐々に高まっています.
現在は,DMT-MMの開発から得られた知見を基に,多方面への応用を目指して研究を実施しています.
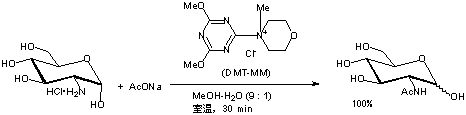
2.人工酵素の開発
私たち生物の生命活動のほとんど全ては,突き詰めれば体の中での化学物質の変化,すなわち化学反応に帰結すると言っても過言ではありません.身体の中での化学反応は,酵素というタンパク質でできた触媒によって行われています.その高度で緻密に制御された機能が発現されるためには,未だ知られざる多くの秘密や謎が隠されています.そのような謎を明らかにし,ひいては化学反応触媒として,その機能を利用することを目指して「人工酵素」の研究が行われています.
多くの酵素モデル研究が加水分解酵素を対象にしていますが,当研究室では,合成化学の観点からより大きな意味を持つ,アシル基転移酵素のモデル開発を行っています.基質を特異的に認識してこれを捕まえる,いわゆる基質結合部位にシクロデキストリンのようなホスト化合物を用いて,基質特異性,反応加速,触媒の代謝回転,生成物による反応阻害の回避などの機能を有するモデル系の確立に成功しました.
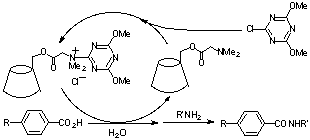
3.反応場としての界面の利用
セッケンに代表される界面活性剤は,水中でミセルやベシクルのようないわゆる分子集合体を形成します.溶液中の分子が3次元的に運動するのに対して,界面に集積した分子は,主として特定の配向性を持つ2次元的な挙動を示します.
Singer-Nicolsonの有名な流動モザイクモデルにおいて,膜内を自由に動くタンパク質は,まさにその典型的な例といえます.
化学反応を効率よくかつ選択的に行うためには,結局のところ「分子運動をいかに制御するか」という問題になります.界面に在る分子は元々自由度が小さいので,自由度の大きな溶液中の分子と比べて制御が容易であると考えられます.そこで,界面の特性をうまく活用すれば,従来の溶液反応では実現出来ないような制御が可能になると期待できます.
このような界面の特性を利用するのに最適な反応の一つに,脱水縮合反応が挙げられます.いわゆるエステルや酸アミドと言われる化合物は,酸とアルコールやアミンから脱水縮合反応によって合成します.もし,これらの反応基質が脂溶性の置換基を持つなら,いずれも両親媒性分子として,反応点が全て界面に集積します.そこで,上述したような水中で進行する脱水縮合反応を利用すれば,医薬品を始めとする様々な化合物の合成に役立つ効率的な反応系になると考え,その確立を目指して研究を行っています.
この研究は独立法人科学技術振興機構による「戦略的創造研究推進事業さきがけタイプ」の「変換と制御領域」に採択され,その支援を受けています.
4.希土類反応剤を用いた素反応開発
ヨウ化サマリウムという試薬は有機溶媒に可溶な一電子還元剤の中では,非常に強力な還元力を有しています.HMPAやアルコール,さらに酸や塩基などの添加剤をうまく利用すると,アルデヒドやケトンはもちろんエステ類,さらに様々な有機ハロゲン化物を還元し,室温,中性と言う温和な条件下でラジカル中間体を経て炭素アニオン発生します.この特性を利用して,ヨウ化サマリウムのベンゼン-HMPA溶液を開発し,特に不安定とされているspあるいはsp2炭素上にラジカルをうまく発生させることに成功し,サマリウムカルベノイドの挿入反応や転位反応,グリニヤール型反応,Wittig型のシグマトロピー転位などを開発しました.現在は反応の選択性を目指して配位子に重点を置いて検討中です.