3)代謝(Metabolism)過程における相互作用
| 薬物相互作用において、最も危険なものは、併用薬による薬物代謝酵素"チトクローム P-450"の抑制に基づく中毒である。一方、併用薬物がこの酵素の活性を高めれば、すなわち酵素誘導が起これば、薬物代謝は促進され、血中濃度も低下し、薬効は減弱する。図6に酵素誘導薬ならびに阻害薬を併用した際の薬物血中濃度の変化を示す。 |
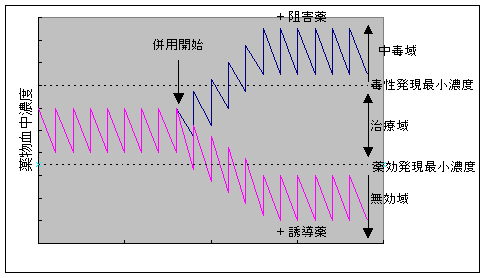
図6 薬物代謝阻害薬ならびに誘導薬併用後の血中濃度変化
| チトクロームP-450 は分子量が5000前後で、鉄分子を一つ含むヘム蛋白質である。 | |
| この酵素は一種類ではなく、表2に示されるように性質の異なる「ファミリー」を形成し、それぞれのファミリーはさらに細分化された酵素群である「アイソザイム」に分れている(表2↓)。 | |
| 最近、薬物の中で、それぞれのアイソザイムにより特異的に代謝されるものと、これらのアイソザイムを特異的に阻害する薬物が明らかにされてきている(表3↓)。 |
| 例えば・・・ |
| 抗アレルギー薬のテルフェナジンはエリスロマイシンやアゾール系抗真菌薬のミコナゾール、イトラコナゾールと併用されると、テルフェナジンの代謝が阻害され、 血中濃度が上昇して、QT時間の延長、さらには Torsades de pointes と呼ばれる心室性不整脈を惹起して死亡することも報告されている。1) |
|
文献 1)P. Periti et al., Clin. Pharmacokinet.,23,132 (1992) |
| 表2 ヒトのチトクロムP-450(CYP)分子種と分類 | |
| 表3 ヒトのチトクロムP-450(CYP)によって代謝、または阻害を受ける主な薬物 |
| チトクロームP-450 はフェノバルビタール、フェニトインなどの抗てんかん剤やリファンピシンなどの投与により酵素誘導が起こり、多くの薬物の代謝を亢進することが知られている(表4↓)。 |
| 例えば・・・ |
| ジクマロールとフェノバルビタールを併用すれば、ジクマロールの血中濃度の低下とプロトロンビン時間の短縮が観察される。 |
| 抗てんかん薬のカルバマゼピンや抗結核薬のリファンピシンはワルファリンの代謝を亢進して、薬効の減弱を招く。 |
| 表4 薬物代謝を誘導する主な薬物と代謝が促進される薬 |
| 以前より、実験動物において、フェノバルビタールなどの投与によりチトクロームP-450 含量が増加することが知られていた。この現象は酵素誘導と呼ばれ、ヒトでも同様な増加が認められる。 |
| 酵素誘導を起こす薬物は、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドン、カルバマゼピンなどの抗てんかん剤や抗結核剤のリファンピシンなどが代表的である(表5↓)。 |
|
|
| 薬物以外では、喫煙もP-450分子種を誘導し、なかでもCYP1A1,CYP1A2を顕著に誘導する。 |
|
| 表5 p-450の誘導と薬物相互作用 |